
マンガを描きながらアマチュア無線を楽しむ日々がつづき、いつのまにか4年が過ぎた1978年の初夏、「テレビマガジン」の編集者から、突然、ラジコンマンガの依頼を受けます。「テレビマガジン」では、その少し前まで連載していた『マシン刑事999』というスーパーカー・アクション・マンガが終わったばかりでした。
担当のIさんは、「スーパーカーのマンガを描いていて、アマチュア無線をやって、ハム仲間とラジコンカーを走らせて遊んでいるんだから、ラジコンマンガも描けるでしょ?」と言うのです。ラジコン自動車は、とても面白くて、自分でも買おうと考え、機種を選定しているときでした。
この頃は、ほかにもレースマンガを数本連載し、取材のために鈴鹿サーキットにも出かけ、モータースポーツ誌の「AUTOSPORT」と「AUTO TECHNIC」は発売日に買って読みふけっていました。Iさんは、そんな状況を知っていて、ラジコンマンガの執筆を持ちかけてきてくれたのです。
でも、すぐにはOKしませんでした。たくさんのアマチュア無線仲間ができ、ときにはアイボールミーティング(ネットのオフ会みたいなものです)と称する飲み会を開いたりと、交友を楽しんでいたときで、そんな趣味の世界を仕事にすることは、仲間を金儲けの道具に使うような気がしたからです。
アマチュア無線は「キング・オブ・ホビー(趣味の王様)」とも称される存在で、そのアマチュア精神が尊重されてもいました。アイボールミーティングに行けば、学生だろうがマンガ家だろうが関係ありません。小学生も一部上場企業のトップも、みな同じハム仲間です。多くの人々と、そんなフラットな人間関係が築けるのも、アマチュア無線にハマった理由のひとつでした。
そのようなわけで、アマチュア無線によってできた仲間と楽しんでいるラジコンを仕事のタネに使うのには、かなりの抵抗を覚えたわけです。
Iさんには、そんなことを話して一度は断りました。ところがIさんは、思わぬ殺し文句を突きつけてきたのです。
「ぼくは、すがやさんほどの適任者は、ほかにいないと思うんだよね。でも、どうしてもイヤだというのなら、ほかのマンガ家さんに頼むしかないけど、すがやさんがそのマンガを見たら、『オレならこうしたのに……』って悔しがると思うよ、きっと」と殺し文句めいたことを言います。そして、「1日だけ待つから考えてみてよ」と言い残して帰っていきました。
そこで私は、一緒にラジコンカーを走らせていた福ちゃんと山ちゃんに連絡をとり、「こんな話があるだけど」と話してふたりに意見を求めました。そうしたらふたりとも「やりましょう、やりましょう!」と大賛成。「ラジコンカーも趣味には違いないけれど、その趣味の楽しさを伝えられるマンガなら、まったく問題はないでしょ」と言ってくれたのです。
これで決心はつきました。すぐにIさんに連絡し、ストーリーは自由に作らせて欲しいとお願いしました。直前まで連載していた『マシン刑事999』は、当初、原作つきのマンガでしたが、アニメのシナリオライターさんが書いた原作は、まさにアニメタッチでリアリティがありませんでした。そこで私が作ったストーリーを提示した結果、原作は使わずに、オリジナルのストーリーで連載をつづけることになりました。Iさんは、私の作るストーリーを買ってくれていたので、このラジコンマンガでも、すべてをまかせてくれることになりました。
それまで「テレビマガジン」や「冒険王」、小学館の学年誌など、小学生向けの媒体で児童マンガを中心にマンガを描いていましたが、その大半は「大人」が主人公でした。コミカライズを担当した『仮面ライダー』シリーズも『マシン刑事999』も、小学生が主人公ではありません。でも、このラジコンマンガでは、『マシン刑事999』のサブキャラとして登場していた大助という小学生を主人公にすることにしました。

子どもを主人公にするうえでイメージしていたのは、小学生から中学生にかけて愛読していた「岩波少年文庫」の世界でした。リンドグレーンの『名探偵カッレくん』やアーサー・ランサムの『ツバメ号』シリーズといった子どもたちの冒険物語です。それに江戸川乱歩の『少年探偵団』のテイストも加え、同時に、ラジコンの知識が身につく情報マンガとしての要素も加えてみたい。こんな狙いを企画書にまとめ、プロットとともにIさんに見せました。
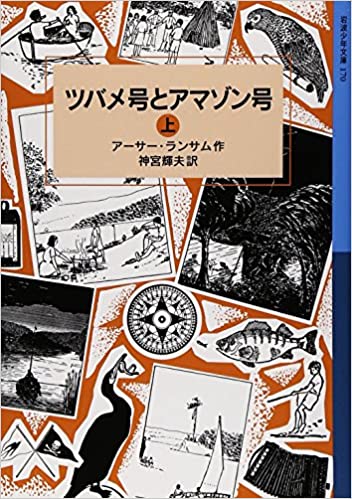
私は、オリジナルマンガを描くとき、自分で企画書を書いて編集者に見せていますが、その企画書を書くようになったのは、このラジコンマンガが最初でした。石森プロで仕事をしていたとき、映像作品の企画書を片っ端から読んでいました。多数の人が関わる映像の仕事では、そのコンセプトなどを周知統一するためのツールとして企画書が不可欠の存在になっています。しかし、マンガの場合はマンガ家と編集者が打ち合わせを重ね、編集会議に提出する企画書は、編集者が書くものと相場が決まっていました。その企画書を自分で書くようにしたのです。
また、企画書に添えた45ページのマンガのためのプロットは、400字詰め原稿用紙で50枚にもなっていました。セリフも入った小説形式の文章で、そのままマンガ原作として使えるようなものでした(これがきっかけで、その後「少年マガジン」に異動したIさんは、私を同誌で〈鶴見史郎〉という原作者に仕立て上げることになります)
前にアマチュア無線をテーマにしたマンガを描いたことはありましたが、ちょっと腰くだけになっていました。登場する無線機やアンテナが「ホンモノ」ではなかったからです。
自分が楽しんでいるホビーのマンガだからこそ、「ホンモノ」を描かなくてはいけない。そう強く意識しました。
このとき思い出していたのは、矢口高雄先生の『鮎』と『幻の大岩魚アカブチ』でした。これらの作品を見習い、「自分の好きな世界を読者にも伝えたい」という想いを込めて描いた作品となりました。
ハム仲間でラジコン仲間の福ちゃん、山ちゃんにも脇役で登場してもらい、描き上げた『ラジコン探偵団』は、『仮面ライダー』総集編の増刊号に掲載されました。大半が『仮面ライダー』のマンガで、オリジナルマンガは2本ほどでしたが、なんと、『ラジコン探偵団』が読者アンケートで1位になってしまったのです。それも7割ほどの票を集めるというダントツの人気でした。
その結果、『ラジコン探偵団』は本誌の別冊フロクで連載になりましたが、ここでも人気はトップを続けることに。コミックスも発売されて増刷もかかる状態だったのですが、テレビ雑誌でオリジナルマンガが1位を続けるのは、ビジネスの上で(おそらく広告スポンサーの関係などから)問題があるのだとか。そのせいで『ラジコン探偵団』は、連載が打ち切られることになってしまったのです。
(次回につづく)